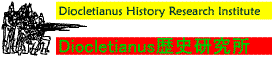今回のテーマは、外交です。
タイトルのとおり、私の外交に対する考え方は、「外交は政治ゲームである」です。
外交を広辞苑で調べてみると、
「外国との交際。国際間の事柄を交渉で処理すること。」とあります。
20世紀に入ってから、兵器の高度化、高性能化に伴い、戦争による(特に、総力戦)人的損害が飛躍的に増大したため、外交交渉から戦争に発展してしまった場合は、悲惨なことになってしまうことも多々ので、ゲームと軽々しく言うのは、はばかられてしまいますが、基本的に、外交が政治的ゲームであるということには、変化はありません。
この外交の政治ゲーム的性質は、西ヨーロッパでよく見受けられます。
中世以降の西ヨーロッパにおける戦争では、勝った側が、負けた側を征服するということは、あまり起きませんでした。(ゼロというわけではありません。)
では、勝った側は、何をしたのでしょうか?
領土の割譲や自国に都合のよい人間を王位につけたり、継承権の獲得などをしていたのです。
つまり、
・領土の割譲は、領土拡大による自国の強化。
・都合のいい人間を王位につけることは、面倒な国の統治はやらずに、自国の安全を守るための方策。
・継承権の獲得は、いざというときに、その国に介入するための口実。
とても、ゲーム的ではないでしょうか。
歴史的に外交の政治ゲーム性を見てみましょう。
場所は、普仏戦争に勝利した後の、プロイセン。
宰相はかの有名な、ビスマルク。
普仏戦争の復讐を狙うフランスに対して、プロイセンの安全を守るために、ビスマルクは次のような外交を展開しました。(<->は敵対関係)
対イギリス---親善関係(当時のイギリスは、最強国で、「栄光ある孤立」をうたっていました。)<->ロシア
対ロシア---三帝同盟、のちに、再保障条約<->オーストリア、イギリス
対オーストリア---三帝同盟、のちに、三国同盟<->ロシア
対イタリア---三国同盟<->フランス
対フランス---敵対
つまり、フランス以外の国々に、仮想敵国、同盟網を作り、フランスとの同盟をしにくくさせていたのです。
このことにより、フランスは、西ヨーロッパ内で孤立することとなり、普仏戦争の復讐をすることはできなくなったのです。
別の例を挙げると、アメリカ独立戦争です。
アメリカ独立戦争は、アメリカの植民地人とイギリスとの戦いですが、アメリカのフランクリンが、ヨーロッパへと渡り、フランスを参戦へと導きました。
その後、イギリスと敵対するスペイン・オランダを参戦へと導き、ロシアのエカチェリーナ2世の提唱で、ロシア・プロイセン・スウェーデン・ポルトガルは武装中立同盟で、イギリスを威嚇したのです。
つまり、軍事的には圧倒的にイギリス側優位であったにも関わらず、外交政策に失敗したために、イギリスは、アメリカの独立を許すこととなってしまったのです。
弱小な者が、強大な敵に打ち勝つ。
これは、とてもゲーム的性質であると思います。
いかがでしょうか?
外交は政治ゲームである
2006/06/03
この文章は、「Diocletianusのつくえ」において投稿された記事とは
若干異なっている可能性がありますのがご了承願います。