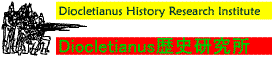今回は、ローマの話題です。
まずは、概略を。
395年の最後の統一ローマ皇帝・テオドシウス1世の2子、ホノリウス(西)、アルカディウス(東)によって、ローマ帝国が分裂しました。
西ローマ帝国が476年にゲルマン人傭兵隊長・オドアケルにより、幼帝・ロムルス=アウグストゥルスが廃位され、滅亡しました。
私なんかは、とても、皮肉に感じてしまいます。
ロムルスとは、ローマの建国者の名前です。
アウグストゥルスは、小アウグストゥスの意のニックネーム、つまり、帝政ローマの創始者の名前なんです。
それが、ローマにあったローマ帝国の最後の皇帝とは・・・。
そんなことは、さておき、東ローマ帝国、俗に言うビザンツ帝国はその後も存続し1453年のオスマン=トルコ帝国のメフメト2世のコンスタンティノープルの攻略まで1000年以上にわたり、存続しました。
さて、この395年の最終的な東西分裂の意義は何であったか?
この問いについて考えたいと思います。
まず、第1は、西欧と東欧がきっぱりと分かれてしまったことにあると思います。
西欧のほうは、西ローマが滅亡し、ゲルマン人国家が割拠する状態となりました。
また、封建制度の成立が促されて、貨幣経済が衰退し、一応、ローマ=カトリック教会による、統一性はあったものの地方分権的な構造が成立しました。
それに対して、東欧では、東ローマがあったゆえに、皇帝による一元支配を保つこととなり、ローマ以来の中央集権が健在し、貨幣経済は存続しました(これも、だいぶ先には崩壊するのですが)。
つまり、西欧は、高度なギリシア=ローマ文明が崩壊し、野蛮なゲルマン民族の支配下に置かれた(簡単にいうと退化)のに対して、東欧では、高度なギリシア=ローマ文明が存続した、ということです。
このことから、西欧諸国は、ビザンツ帝国を、うらやましげに指をくわえながら眺めるという状況が生まれたのです。
第2にキリスト教に対する考え方が、やはり西と東で別れてしまいました。
世界史を学んでいる、あるいは、学んだ方にとっては、おなじみですが、ビザンツでは、皇帝教皇主義(皇帝が聖俗ともに権力を持つという考え方)が確立し、西方では、聖俗の分離が図られた、というのはご存知でしょう。
しかし、世界史では、教えてもらえませんが、東西分裂以前のローマ帝国においては、皇帝教皇主義が基本路線であったそうです。
325年のローマ皇帝・コンスタンティヌス1世による、エフェソス公会議以来、皇帝が、キリスト教の教義について介入することが多々あり、それが当然だと人々の間では考えられていたようです。
これらのことから、キリスト教の管理は、皇帝がするもの、という考えが生まれたのです。
これを元に、皇帝教皇主義が確立したといえるのです。
しかし、西欧では、宗教を管理する皇帝がいなくなったため、ローマ=カトリック教会は、カール大帝の戴冠以来、自らの手で西ローマ皇帝を作り出し、東ローマに対抗するようになったのです。
なぜなら、あまりにも、ヨーロッパ世界にとって、ローマが偉大すぎたがゆえに、ローマ皇帝とキリスト教の2枚のカードがそろって、初めてヨーロッパ世界を統治できるという考え方が生まれていたからです。
逆に、東欧では、皇帝と宗教の双方が健在であったがために、ローマ帝国の時代から、成立しつつあった皇帝教皇主義が確立されたのです。
ローマ帝国の分裂
2006/05/29
この文章は、「Diocletianusのつくえ」において投稿された記事とは
若干異なっている可能性がありますのがご了承願います。