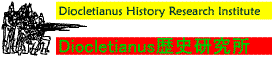前回は、ナポレオンの話をしました。
同様の例で、旧日本軍のインパール作戦も、山地によって、補給が困難であったにもかかわらず、強行されたので、失敗したのです。
今回は、普仏戦争のプロイセンの勝利について書いてみたいと思います。
普仏戦争で、なぜ、プロイセンはフランスに勝利できたか。
逆に、なぜ、フランスはプロイセンに敗北したか。
この普仏戦争は、プロイセンのあの有名な鉄血宰相、ビスマルクによる、情報操作に端を発します。
ビスマルクは、国王ヴィルヘルム1世からの電報を改ざんしたのです。(エムス電報事件)
ビスマルクは、かねがね、フランスとの戦争を想定し、大モルトケとともに、フランス侵攻の作戦を何度も練っていました。
国境付近に軍の情報将校を派遣して、フランスの地図を作らせるなど、準備を周到に行っていたのです。
この電報事件の2日後、フランスは、動員令を発布し、その4日後にプロイセンに対し、宣戦を布告しました。
プロイセンは、フランスの動員令の翌日に動員令を発布し、宣戦布告に応えました。
結果は、始終プロイセン軍が人員、作戦ともに、フランス軍を圧倒し、セダンでナポレオン3世を捕虜にし、プロイセン軍の完全勝利に終わります。
作戦でフランス軍を圧倒していたことは、先にも述べたとおり、何度も作戦を練り直したり、地図がきちんと用意されていたから、というようにわかります。
しかし、なぜ、プロイセンはフランスよりも、多くの兵士を用意することができたのでしょうか。
両国の動員令の発布の時間差は1日しかなく、あらかじめ、国境付近に軍を配備していたとは考えられません。
そんなことしたら、ビスマルクが、電報を改ざんしたことが、ばれるしね。
答えは、ビスマルクらしい、鉄と血であったのです。
まずは、鉄から。
この鉄は、鉄道の鉄です。
フランスとの戦争を想定していたプロイセンは、国土を東西に横断する鉄道を6本も敷設していました。
このことにより、ロシア、オーストリアなど対諸外国防衛のための軍を素早く、対フランスのために、移動することができたのです。
次に血。
この血は、兵員を意味します。
プロイセンは、当時には珍しく、国民皆兵制をとっていました。
つまり、兵員の絶対数がフランスよりも多かったことになるのです。
つまり、プロイセンは、国民皆兵制によって得た、多数の兵力を、鉄道によって、もてあますことなく、かつ、迅速に対フランス戦線に配備することが可能であったのです。
ですから、軍の準備がフランスよりも、素早く、かつきちんと行えたのです。
大量の兵士を前線に送ることのできる制度は、立派な兵站の一部であるといえますし、もちろん、東西を横断するように敷設された6本の鉄道は兵站の一部です。
つまり、この普仏戦争におけるプロイセンの勝利は、綿密な作戦と、それを可能にする兵站によって、もたらされたといっても過言ではないのです。
まだまだ、続きます。
Logistics (兵站)がものをいう-III
2006/04/28
この文章は、「Diocletianusのつくえ」において投稿された記事とは
若干異なっている可能性がありますのがご了承願います。